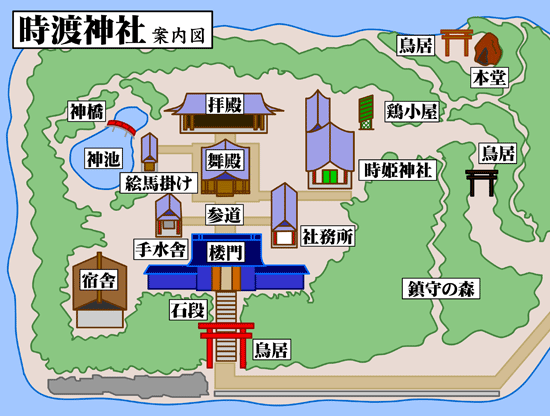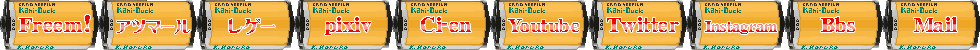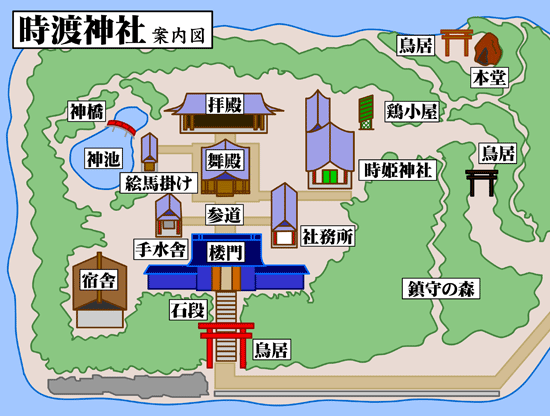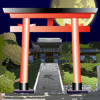 |
鳥居・石段・楼門(とりい・いしだん・ろうもん)
神社の入口には、境内と俗界の境界を示す鳥居があり、社殿まで参道が通じる。
階段は煩悩の数(一〇八段)あり、主人公は登るのが嫌い。 |
 |
手水舎(ちょうずや・てみずや)
参拝者が身を浄めるために手水を使う施設のこと |
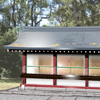 |
社務所(しゃむしょ)
御守りや絵馬やお札等を売る売店的な役割と、社務(事務)を取り扱っている窓口
雀と雪加の2人のアルバイトを雇っている |
 |
舞殿(まいぶ)
舞楽を行うための建物(神楽殿 かぐらでん)
神の御意を慰めるために舞や神楽を奏する建物。
祭りの時に比奈が踊るらしい |
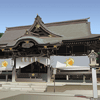 |
拝殿(はいでん)
神に参拝するための物 |
 |
本殿(ほんでん)
実際に御神体などに宿る神が鎮座して居る
時渡神社には直接本堂(御神体)が無い、川を上っていった山の裏側の祠にあり
危険なので誰も行けない |
 |
神池・神橋(かみいけ・しんきょう)
大きな神社ではあることがある。本殿や神社の境内などに架けてある橋。 |
 |
鎮守の森(ちんじゅのもり)
神社のまわりにある森林のこと。神社に付随して参道や拝所を囲むように設定・維持されている森林。 |
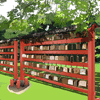 |
絵馬掛け(えまかけ)
絵馬は祈願するとき、および祈願した願いが叶って、その謝礼をするときに寺社に奉納します。生きた馬の代わりに絵に描いて奉納したのが始まりと言われています。屋根形の小絵馬や大形の額絵馬などがある。 |
 |
二之鳥居(にのとりい)
裏道と呼ばれているもう一方の入り口
舗装されて無く街頭なども無いため誰も使わず鳥居などは腐敗してきている
危険なのであまり使われない |
 |
時姫神社(ときひめじんじゃ)
神社の中にある小さな神社
現在閉鎖中で入れない。主人公も入ったことがない。
鳥居が多きのが特徴。
|
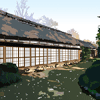 |
宿舎(しゅくしゃ)
主人公達が寝泊まりしている場所 |
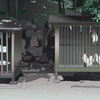 |
鶏小屋(とりごや)
鶏を飼っている |